「星座」それに「暦」のそれぞれの歴史について紹介しましたが、次は、天文学が発展する要因の1つになった望遠鏡の発明とその歴史についても調べてみましたので、興味がありましたならばお読み下さい。
 望遠鏡の発明と歴史
望遠鏡の発明と歴史
 望遠鏡の原理がレンズを組合わせることによって物が大きく見えることは、今では誰でも知っていると思いますが、望遠鏡の歴史を紹介する上で重要になるのは、レンズの歴史を知る必要があります。
望遠鏡の原理がレンズを組合わせることによって物が大きく見えることは、今では誰でも知っていると思いますが、望遠鏡の歴史を紹介する上で重要になるのは、レンズの歴史を知る必要があります。レンズの語源はレンズ豆(ラテン語: Lens)で、当初作られたレンズは凸レンズであり、その形状がレンズ豆に似ていたことからこの名前が付いたそうです。
現在確認されている世界最古のレンズは、ニムルド(現在のイラク北部ニーナワー県)にある、紀元前7世紀の古代アッシリアの墓から1853年に発見された水晶製のレンズだそうです。しかし、実際は飾りとして埋め込まれたもので、レンズとしての効果は偶然の産物ではないかとみられているそうです。ユーラシア大陸の古代文明において、レンズは着火用に用いられていたそうです。
当初、水晶や宝石を磨いてレンズの形に整形した物で、非常に高価な品で庶民には縁の遠い貴重品で、一部の王族や貴族だけがレンズを使っていたそうです。
偶然の産物として生まれたレンズが、無色透明なガラスで作られるようになったのはいつ頃なのか気になり調べてみました。
ガラスの歴史は古く、紀元前4世紀より前にエジプトやメソポタミアで二酸化ケイ素の表面を融かして作製したビーズが始まりだと考えられているそうです。当時は、ガラス自体を材料として用いていたのではなく、陶磁器などの製造と関連しながら用いられていたと考えられていて、原料の砂に混じった金属不純物などのために不透明で青緑色に着色したものが多数出土しているそうです。紀元前1世紀の後半になると、エジプトのアレクサンドレイアで、宙吹きと呼ばれる製造法が発明され、この技法は現代においても使用されるガラス器製造の基本技法で、これによって安価なガラスが大量に生産され、食器や保存器として用いられるようになったそうです。
中世の8世紀頃から、西ヨーロッパでもガラスの製作が再開され、12世紀には教会にゴシック調のステンドグラスが備わるようになり、13世紀には不純物を除いた無色透明なガラスがドイツ南部やスイス、イタリア北部に伝来して、眼鏡の材料となるレンズにも流通するようになり、レンズは庶民でも手に入れられる製品になったそうです。
歴史上で最初に作られた望遠鏡は屈折式で、凸レンズを対物レンズに、凹レンズを接眼レンズとして使用したものだったそうです。この望遠鏡の発明者は諸説あって明確ではないそうです。
その中で、オランダのメガネ職人ハンス・リッペルスハイは、彼の店で遊んでいた2人の子供が、1枚のレンズの前にもう1枚のレンズをかざした時に物がはっきり見えることに気付き望遠鏡の着想を得て、1608年に30年間の特許申請をした記録が残っていることから、この方式の望遠鏡はオランダ式望遠鏡と呼ばれているそうです。
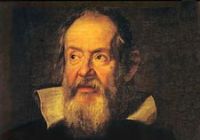 オランダ国会は、疑わしい点もあることから特許権を与えなかったが、軍事に関連する製作法と考えられ秘密を厳守するよう申し渡したそうです。しかし、2枚のレンズを組合わせるという重要なヒントが特許申請により公知となり、その情報が急速に広まったそうです。
オランダ国会は、疑わしい点もあることから特許権を与えなかったが、軍事に関連する製作法と考えられ秘密を厳守するよう申し渡したそうです。しかし、2枚のレンズを組合わせるという重要なヒントが特許申請により公知となり、その情報が急速に広まったそうです。1609年7月にガリレオ・ガリレイは、「オランダで望遠鏡が発明された」という話を聞き、暫く考えると、凸レンズと凹レンズを一直線に配置すれば望遠鏡ができことを解き、口径:42mm、長さ:2.4m、9倍の望遠鏡を自作したそうです。
ガリレオは、自作した望遠鏡を使って、月面の凹凸や金星の満ち欠けなど数々の発見をします。その中でも、木星の衛星を観測して、その公転周期を求め航海用の時計とすることを提案したことは有名で、この4つの木星の衛星は、今でもガリレオ衛星と呼ばれています。 このように、この方式の望遠鏡で多くの発見をしたガリレオ・ガリレイの話と共に伝わってきた歴史から、日本ではガリレオ式望遠鏡と呼ばれることが多いそうです。
ドイツ人で天文学者のヨハネス・ケプラーは、1611年に凸レンズを接眼鏡に使う望遠鏡を設計して発表したそうです。その望遠鏡を自分では製作しなかったが、同じドイツ人で天文学者のクリストフ・シャイナーが、1615年にケプラーが設計した望遠鏡を製作して天体観測にも使用したそうです。これがケプラー式望遠鏡で、現在の天体望遠鏡の基礎となっているそうです。
ガリレオが作ったガリレオ式望遠鏡(オランダ式望遠鏡)は正立像でしたが、ケプラー式は倒立像になります。ガリレオ式で問題だった倍率を上げると急激に視界が狭くなるという短所を解消して、対物レンズの焦点面にも合焦するため、そこに糸を張れば十字線や測量微尺として使用でき、測量等に非常に大きな意義を持ったた望遠鏡だそうです。
また、天体望遠鏡として使用する場合には、像の倒立は欠点にならずに、正立プリズムを挿入すことで正立像が得られることから地上望遠鏡としても広く使われているそうです。
ヨハネス・ケプラーは、惑星の軌道を楕円と仮定するとティコ・ブラーエの観測した結果を説明できることが分かり、後に「ケプラーの法則」とされ、これによってようやく地動説が、従来の天動説よりも単純で正確なものとなったそうです。
 望遠鏡は、対物レンズの口径を大きくすればするほど解像力が増して、天体の詳細が観測できるので、対物レンズの直径は徐々に大きくなっていったそうです。しかし、対物レンズの直径が大きくなればなるほど、また観測する倍率を上げれば上げるほど、色収差と呼ばれる像の着色が顕著になり、解像度を下げる要因になります。
望遠鏡は、対物レンズの口径を大きくすればするほど解像力が増して、天体の詳細が観測できるので、対物レンズの直径は徐々に大きくなっていったそうです。しかし、対物レンズの直径が大きくなればなるほど、また観測する倍率を上げれば上げるほど、色収差と呼ばれる像の着色が顕著になり、解像度を下げる要因になります。その解決策として、対物レンズの直径に対する焦点距離を長くすれば色収差を抑えることができるので、ポーランドの天文学者であるヨハネス・ヘヴェリウスは、1673年にレンズの直径15cmで鏡筒に当たる部分の長さが45mにもなる空気望遠鏡(鏡筒部分がない望遠鏡)を制作して、公開で天文観測を行ったそうです。「ヘヴェリウスの空気望遠鏡」は彼の代名詞であり、空気望遠鏡と言えばヘヴェリウスの名が第一に挙げられるそうです。しかし、あまりに巨大であったために風や震動の影響を受けやすく、観測は巧く行かなかったそうですが、1682年に到来したハレー彗星の観測では成果を挙げたそうです。
また、オランダの天文学者であるクリスティアーン・ホイヘンスは、1656年に長さ37mの空気望遠鏡で土星の環の形状を確認したことや、オリオン大星雲を発見してスケッチを残して、これが最初のオリオン大星雲のスケッチとなったそうです。
屈折式望遠鏡の宿命である色収差を解決するために巨大な空気望遠鏡が出現する中で、オランダのメガネ職人のハンス・リッペルスハイがオランダ式望遠鏡(ガリレオ式望遠鏡)を発明してから約半世紀が経過した1663年に、スコットランド生まれの天文学者:ジェームス・グレゴリーは、鏡(ミラー)を用いて光を集める反射式望遠鏡を考案して公表したそうです。この反射式望遠鏡の主鏡は放物凹面鏡で、副鏡は楕円凹面鏡になっていて、主鏡の中央に穴があってそこから光を後方に導く方式で、グレゴリー式望遠鏡と呼ばれているそうです。
 万有引力の発見者であるイングランドのアイザック・ニュートンは、1668年に現在の反射式望遠鏡の原型となるグレゴリー式望遠鏡を改良した第1号機を完成したそうです。この方式は、凹面鏡(主鏡)で反射させた光を、光軸上前方に置いた斜め45度の平面鏡で横方向に取り出した後レンズを通して覗く方式で、ニュートン式望遠鏡と呼ばれています。
万有引力の発見者であるイングランドのアイザック・ニュートンは、1668年に現在の反射式望遠鏡の原型となるグレゴリー式望遠鏡を改良した第1号機を完成したそうです。この方式は、凹面鏡(主鏡)で反射させた光を、光軸上前方に置いた斜め45度の平面鏡で横方向に取り出した後レンズを通して覗く方式で、ニュートン式望遠鏡と呼ばれています。この他にも多くの方式の反射式望遠鏡が考案されますが、これらの反射式望遠鏡はレンズの屈折によらず、鏡で光を反射し光を集めるので、屈折式望遠鏡で悩まされた色収差(色ずれ)が発生しないため、鏡を精度よく磨けば、口径比が小さくてもシャープな像を得ることができ、屈折式望遠鏡に比べてコンパクトにできたそうです。
こうして反射式望遠鏡の出現により、口径20cmほどで止まっていた望遠鏡の口径は一気に大口径化していったそうです。
当初の反射式望遠鏡に使われいた反射鏡は、現在のようなガラスにアルミコーティングをしたものではなく、金属を磨いて光を反射させる金属鏡で、スズや銅などの合金が使われ、研磨機で研磨して作成していたそうです。
その後、1830年頃にイギリスでガラスに銀メッキする方法が発明され、これがレオン・フーコーに伝わり、1859年に反射式望遠鏡に用いる反射鏡の表面形状を精密に検査する方法を論文として発表したことで、1860年代からイギリスでは多数の多くのアマチュアが銀メッキガラス鏡を製作するようになり、現在の反射式望遠鏡の原型がこの時作られたそうです。
屈折式望遠鏡は、対物レンズの直径が大きくなればなるほど、また観測する倍率を上げれば上げるほど、色収差と呼ばれる像の着色が顕著になるという問題があり、次第に反射式望遠鏡が主流になったそうです。しかし、1729年にイギリスのチェスター・ムーア・ホールは、屈折率の異なる2種類のガラス材を組合わせて対物レンズを作り、色収差を大幅に抑えたアクロマートレンズを開発したそうです。
更に、3種類のガラス材を組合わせたアポクロマートレンズが開発され、「アクロマートレンズより向上したレンズ」という意味になり、カメラ用レンズや望遠鏡にも使用されるようになったそうです。
その後、1886年にドイツのフリードリッヒ・オットー・ショットによって非分散光学ガラスが開発され、アポクロマートレンズ(EDレンズ)をアッベの依頼により開発したそうです。異常部分分散性を持ったガラスを使った異常分散レンズ(EDレンズ)が開発されたことにより、色収差の少ないアポクロマートを実現するために用いられ、非常に色収差の少ない像を得ることができ、高性能を要求する光学機器、特にカメラ用レンズ,顕微鏡,望遠鏡などに用いられるようになったそうです。
以前の空気望遠鏡では、対物レンズの大きさの数十倍以上必要だった焦点距離が、EDレンズの開発によって短くて済むようになり、とてもコンパクトになったことから、次々と口径の大きな屈折式望遠鏡が作られるようになったそうです。
このように望遠鏡の歴史を知ることで、屈折式望遠鏡と反射式望遠鏡には、それぞれに長所・短所があることが分かります。特に、対物レンズや主鏡で集められた光の像のシャープさを損なう要因を「収差」といって、屈折式望遠鏡では、対物レンズの屈折率によって色収差が、反射式望遠鏡の場合には、放物凹面構造の主鏡の光軸に対して斜めに入ってくる光が片ボケするコマ収差があるそうです。
それぞれの収差については、「収差」を参考にして下さい。
最後に、有名な光学望遠鏡を紹介します。
 |
ハッブル宇宙望遠鏡(HST)は、地上約600km上空の軌道上を周回する宇宙望遠鏡で、名称は宇宙の膨張を発見した天文学者:エドウィン・ハッブルの名を採って付けられたそうです。長さ13.1メートル、重さ11トンの筒型で、内側に反射式望遠鏡を収めていて、主鏡の直径2.4メートルのいわば宇宙の天文台で、大気や天候による影響を受けないため、地上からでは困難な高い精度での天体観測が可能だそうです。 |
 |
日本の国立天文台がハワイ州のマウナ・ケア山に建設したすばる望遠鏡は、口径8.2mで、単一鏡の反射式望遠鏡としては、2008年に大双眼望遠鏡(LBT)が建設されるまで最も口径が大きかったそうです。すばる望遠鏡には高度な技術が多数使われていて、コンピュータで制御された261本のアクチュエータにより主鏡を裏面から支持することにより、望遠鏡を傾けた時に生じる主鏡の歪みを補正して、常に理想的な形に保たれているそうです。 |
 |
大双眼望遠鏡(LBT)は、アリゾナ州南東部のグラハム山の標高3,260メートル地点に位置する天文観測施設で、2008年時点において、世界で最も分解能のすぐれた反射式望遠鏡で最も先進的な光学望遠鏡だそうです。望遠鏡は2枚の8.4m鏡が同一の架台に並べて取り付けられていることから双眼鏡と呼ばれているそうです。 なお、近赤外線での像はハッブル宇宙望遠鏡よりも10倍分解能が高い望遠鏡だそうです。 |
ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/
すばる望遠鏡:http://subarutelescope.org/j_index.html
他
