地球から一番近い天体といえば月で、昨年(2016年)の11月14日は68年ぶりに最接近するスーパームーンが見れると話題になりましたが、その月について調べてみましたので興味がありましたならばお読み下さい。
 月
月
 月は地球の唯一の衛星で、太陽系の衛星の中で5番目に大きく、地球から見て太陽に次いで明るいそうです。そのことから、古くから月を愛でる(美しさを味わい感動する)行事として「月見(観月)」があり、その代表的なものに「中秋の名月(十五夜)」や「十三夜」があるそうです。
月は地球の唯一の衛星で、太陽系の衛星の中で5番目に大きく、地球から見て太陽に次いで明るいそうです。そのことから、古くから月を愛でる(美しさを味わい感動する)行事として「月見(観月)」があり、その代表的なものに「中秋の名月(十五夜)」や「十三夜」があるそうです。旧暦8月(グレゴリオ暦9月頃)は乾燥していて月が鮮やかに見え、また月の昇る高さもほどよく、気候的にも快適なため月見に良い時節とされ、主に旧暦8月15日から16日の夜(八月十五夜)と、日本では旧暦9月13日から14日の夜(九月十三夜)にも行われるそうです。中秋の名月は、旧暦の8月15日から16日に見る月のことから、満月とは限らないそうです。
写真は、旧暦の8月15日に満月となった2013年9月19日の中秋の名月を撮影したものです。次に満月の中秋の名月を見ることができるのは、8年後の2021年だそうなので、みなさんもご覧になっては如何でしょうか。
その他にも、月を愛でたと思われることばがいくつもあり、寒月(かんげつ),雨月(うげつ),雪待月(ゆきまちづき)それに薄月(うすづき)などがあるそうです。そこで、月に纏わることばなどから、月について調べてみましたので紹介します。
地球から月までの距離は、平均距離:384,400Kmで地球を9周半分した距離に相当するそうです。但し、いつも同じというわけではなく、地球と月はこの距離より近くなることも遠くなることもあるそうです。 地球と月の距離が変化するのは、地球を周回する月の公転軌道が円軌道ではなくて楕円軌道だからだそうです。月の軌道が楕円であるために、月が軌道のどの位置にあるかによって、地球から月までの距離は約357,000kmから406,000kmまで変化するそうです。この軌道上で月が最も地球に近づく点を「近地点」、反対に最も遠くなる点を「遠地点」と呼ぶそうです。月はこの軌道上を公転しながら、 近地点〜遠地点〜近地点〜と、その位置を変えるために、地球と月の距離は月が地球の周りを公転する毎に、遠近の変化を繰り返すことになるそうです。
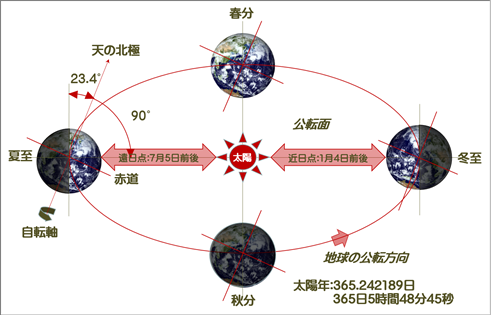
しかし、近地点の距離も、37万kmの時もあれば36万kmを切る時もあり、毎回同じではないそうです。
月の近地点、遠地点の距離が毎回変化するのは、月の公転運動に地球以外の天体の引力も作用するためで、こうした副次的な作用の内、最大のものは太陽によって引き起こされるもので、「太陽摂動(たいようせつどう)」と呼ばれているそうです。太陽摂動によって月の軌道の形状がどのような影響を受けるかを示したものが赤色の点線で、月の軌道は、太陽に最も近づく位置(新月の位置)と、その反対の太陽から最も遠い位置(満月の位置)で地球に近づく形に変形されるそうです。月が地球に最も近づく近地点付近で新月か満月を迎えると太陽摂動の影響が加わって、月は普段の近地点通過時より更に地球に近づき、スーパームーン(Super Moon)と呼ばれる状態になるそうです。
 ちなみに、昨年(2016年)の11月14日は68年ぶりに最接近するスーパームーンが見れると話題になった時の距離は356,511kmだったそうです。平均距離と比較すると27,889Kmも近づいたことになります。そのため、近地点の満月は、遠地点のものよりも最大14%大きく30%明るいそうです。
ちなみに、昨年(2016年)の11月14日は68年ぶりに最接近するスーパームーンが見れると話題になった時の距離は356,511kmだったそうです。平均距離と比較すると27,889Kmも近づいたことになります。そのため、近地点の満月は、遠地点のものよりも最大14%大きく30%明るいそうです。残念ながら関東地方は曇りで時々雨も降り、観察することができませんでしたので、写真は、2015年9月28日に撮影したスーパームーンと、それよりも2ヶ月前の満月(ブルームーン)を比較したものを貼り付けてみましたが、僅か2ヶ月の違いでも大きくなっていることが分って頂くると思います。この時の月までの距離は356,876kmだったので、昨年よりも365Km遠かったことになります。
「ちょっと一休み!」
なぜ、月の裏側を見ることができないのか?
月は、太陽系の惑星やほとんどの衛星と同じく、天の北極から見て反時計周りの方向に公転しているそうです。軌道は円に近い楕円形をしていて自転周期は27.32日で、地球の周りを回る公転周期と完全に同期しているそうです。そのために、地球上から月の裏側を直接見ることは永久にできないのだそうです。
これはそれほど珍しい現象ではなく、火星の2衛星、木星のガリレオ衛星であるイオ,エウロパ,ガニメデ,カリスト、土星の最大の衛星タイタンなどにも見られるそうです。
これに対して、天文学的な二分二至は1年間を4等分はせずに、太陽黄道を0°,90°,180°,270°で4等分するためわずかに差があり、1年に13回の満月があるとその1つがブルームーンになるため、ブルームーンは閏月と同様に2〜3年間隔で、19年に7回起こるそうです。ブルームーンとなるのは、二分二至の約2ヵ月後で次の二分二至の約1ヶ月前となり、2月,5月,8月,11月のいずれかの21日頃で、雨水・小満・処暑・小雪頃のいずれかとなるそうです。
| 季節 | 順序 | およその出現期間 | 呼び名 | |
|---|---|---|---|---|
| 春 | 第1 | 3月21日 | 4月19日 | Egg moon(卵の月) |
| 第2 | 4月20日 | 5月20日 | Milk moon(乳の月) | |
| 最後 | 5月21日 | 6月19日 | Flower moon(花の月) | |
| 夏 | 第1 | 6月20日 | 7月20日 | Hay Moon(干草の月) |
| 第2 | 7月21日 | 8月19日 | Grain Moon(穀物の月) | |
| 最後 | 8月20日 | 9月19日 | Fruit Moon(果実の月) | |
| 秋 | 第1 | 9月20日 | 10月19日 | Harvest Moon(収穫の月) |
| 第2 | 10月20日 | 11月18日 | Hunter’s Moon(狩人の月) | |
| 最後 | 11月19日 | 12月19日 | Moon Before Yule(ユール前の月) | |
| 冬 | 第1 | 12月20日 | 1月18日 | Moon After Yule(ユール後の月) |
| 第2 | 1月19日 | 2月18日 | Wolf Moon(狼の月) | |
| 最後 | 2月19日 | 3月20日 | Lenten Moon(四旬節の月) | |
| - | 第3 | - | - | Blue Moon(青い月) |
[ブルームーンの発生周期]
30.436875日(1ヶ月の平均)-29.530585日(平均朔望月)=0.90629日
0.90629日x12ヶ月=10.87548日
29.530585日/10.87548日=2.71582年
19年x12ヶ月=228ヶ月
228ヶ月x0.90629日=206.63412日
206.63412日/29.530585日=6.99729回
ところが、1946年に天文雑誌「スカイ&テレスコープ」(アメリカのアマチュア天文学分野の月刊誌)がこれを誤って、ひと月の内に満月が2回ある場合に、その2つ目をブルームーンと掲載したために、現在においてもこの記事の内容をそのまま引用している例が多いのだそうです。 月の満ち欠けは、平均29.530585日を周期として繰り返され、グレゴリオ暦の1暦月の長さは平均30.436875日(最大:31日)なので、月の初めに満月になると、その月の終わりに再び満月が巡ってくる場合がある。 この現象も2〜3年間隔で起こる。但し希に、同じ年の1月と3月に起こり、代わりに2月に満月が1度もないことがあるが、これは2月が1朔望月より短いため起こるのだそうです。
2010年〜2020年に起こるブルームーンは以下の通りだそうです。
2012年8月2日,31日
2015年7月2日,31日(写真は2915年7月31日に撮影)
2018年1月2日,31日
2018年3月2日,31日
2020年10月1日,31日
以前は、海外では不吉なことへの前兆と言われていたが、近年では「ブルームーンを見ると幸せになれる」と言われるようになったそうですので、星空が見える晴れた日ならば、是非夜空を眺めてみては如何でしょうか。
ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/
宇宙航空研究開発機構(JAXA):http://www.jaxa.jp/
宙(そら)の名前 執筆者:林 完次 発行:角川書店
他
