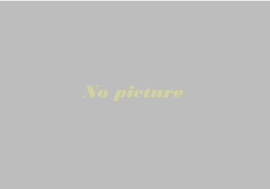星の名前(和名)とそれに纏わる由来について調べてみましたので、興味がありましたならばお読み下さい。
 星の名前(和名)と由来
星の名前(和名)と由来
紀元前3,000年頃の古代エジプト人は、シリウス(Sirius)のことを水の上の星(ソティス)として重要視していたそうです。それは、全天で一番明るい星であったということと、夏至の頃の日の出直前に現れると間もなくナイル川の増水が始まり、洪水の時期に周期性があることに気付き、人類が農耕を行うようになると、適切な農作業の時期を知るのに重要なものとなったからだそうです。
シリウス(Sirius)は、太陽を除けば地球上から見える最も明るい恒星で、ギリシャ語で「焼き焦がすもの」や「光り輝くもの」を意味する「セイリオス(Seirios)」に由来するそうですが、日本での星の名前とそれに纏わる由来についてを調べてみましたので紹介します。なお、各写真をクリックして拡大写真をご覧下さい。
 星に付けられた名前(和名)
星に付けられた名前(和名)
 アルクトゥールス(Arktoyros)の和名:麦星(愛媛・静岡・岡山)、麦刈星、麦熟れ星、五月雨星
アルクトゥールス(Arktoyros)の和名:麦星(愛媛・静岡・岡山)、麦刈星、麦熟れ星、五月雨星
 |
アルクトゥールス(Arktoyros)は、うしかい座のα星で、うしかい座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つです。実視等級がマイナスとなる4個の恒星(太陽を除く)の内の1つです。
[由来]
麦星などは、麦を刈り入れる頃になると日没後にアルクトゥールスが頭上に輝くことから名付けられているそうです。 |
 スピカ(Spica)の和名:真珠星(福井)、春の夫婦星
スピカ(Spica)の和名:真珠星(福井)、春の夫婦星
 |
スピカ(Spica)は、おとめ座のα星で、おとめ座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つで、春の夜空に青白く輝くので容易に見つけることができます。
[由来]
野尻抱影は40年以上この星の和名を探したものの、僅かに福井県日高郡で「しんじぼし」と呼ばれていた星をスピカと推定して、その語源を「真珠」と類推したそうです。
赤っぽく輝くアルクトゥールスを男性、白く輝くスピカを女性のカップルに見立てた「春の夫婦星」の呼び名もあるそうです。 |
※野尻 抱影(のじり ほうえい)
英文学者,随筆家,天文民俗学者で、古今東西の星座・星名を調べ上げたことから、星の和名の収集研究で知られるそうです。日本各地の科学館やプラネタリウムで行われる、星座とその伝説の解説には、彼の著作が引用されることが多いそうですが、星の和名の収集を始めたのは40歳を過ぎてからだそうです。
 カノープス(Canopus)の和名:布良星(めらぼし)(千葉)、横着星(おうちゃくぼし)
カノープス(Canopus)の和名:布良星(めらぼし)(千葉)、横着星(おうちゃくぼし)
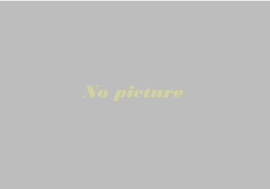 |
カノープス(Canopus)は、りゅうこつ座のα星です。りゅうこつ座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つで、太陽を除くとシリウスに次いで全天で2番目(-0.72等星)に明るい恒星です。
[由来]
房総半島の南端の布良(めら)という漁港に「布良星(めらぼし)」という呼び名があり、この方向に見える星という意味合いがあるそうです。その他にも、南の空にちょっと昇って直ぐ沈むので「横着星」の呼び名があるそうです。 |
 ベガ(Vega)の和名:織姫、織女(星)
ベガ(Vega)の和名:織姫、織女(星)
 |
ベガ(Vega)は、こと座α星で、こと座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つです。わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブと共に、夏の大三角を形成しています。
[由来]
織姫(おりひめ)は、彦星(わし座のアルタイル)、すばる(おうし座のプレアデス星団)と共に、現在も使われることのある数少ない星の和名の1つだそうです。
日本では織女(星)ともいうそうですが、元は中国から伝わってきたものだそうです。 |
 アルタイル(Altair)の和名:彦星、犬かい星、牛かい星
アルタイル(Altair)の和名:彦星、犬かい星、牛かい星
 |
アルタイル(Altair)は、わし座のα星で、わし座で最も明るい恒星で全天に21個あるの1等星の1つです。アルタイルは非常に高速で自転(毎秒240キロ、8.9時間で1周)しているために楕円形をしていて、赤道の直径は極側の直径より14%膨らんでいるそうです。
[由来]
こと座のベガと共に、彦星(牽牛星)は七夕の伝説としてよく知られています。 |
 デネブ(Deneb)の和名:古七夕(京都)、天の川星(岐阜)
デネブ(Deneb)の和名:古七夕(京都)、天の川星(岐阜)
 |
デネブ(Deneb)は夏を代表する恒星の1個で、はくちょう座のα星です。はくちょう座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つです。こと座のベガ、わし座のアルタイルと共に、夏の大三角を形成しています。
[由来]
「古七夕」を「後七夕(あとたなばた)」とも呼ばれ、七夕の2星(ベガ,アルタイル)よりも遅れて輝きだすことから付けられたものだそうです。 |
 アルデバラン(Aldebaran)の和名:後星(青森)、統星の後星(青森・岩手)、赤星(石川・北海道)
アルデバラン(Aldebaran)の和名:後星(青森)、統星の後星(青森・岩手)、赤星(石川・北海道)
 |
アルデバラン(Aldebaran)は、おうし座のα星であり、おうし座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つです。冬のダイヤモンドを形成する恒星(6個)の内の1つでもあります。
[由来]
アルデバランという名前は、アラビア語のアッ・ダバラーンに由来していて「後に続くもの」という意味であるそうです。日本にも、後星(あとぼし)、統星の後星(すばるのあとぼし)、統星の尾の星など、アラビア語と同じ発想の名前が残っているそうです。また、赤星という、色に着目した名前もあるそうです。 |
 アンタレス(Antares)の和名:赤星(長野・静岡)、酒酔い星(大分・山口)、豊年星(佐賀・香川)
アンタレス(Antares)の和名:赤星(長野・静岡)、酒酔い星(大分・山口)、豊年星(佐賀・香川)
 |
アンタレス(Antares)は、さそり座のα星で、さそり座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つです。夏の南の空に赤く輝くことでよく知られる恒星で脈動変光星ですが、実際の変光範囲は0.9等~1.2等で眼視観測ではほとんど分からないそうです。
[由来]
さそり座は黄道十二宮の1つで、火星と接近して見える場合があり、共に明るく赤い星であることから、アンタレスはギリシャ語で「火星(アレース)に対抗(アンチ)するもの」を意味する名が付けられたもので、和名の赤星なども星の色に由来しているそうです。 |
 フォーマルハウト(Fomalhaut)の和名:秋の1つ星、南の1つ星、秋星
フォーマルハウト(Fomalhaut)の和名:秋の1つ星、南の1つ星、秋星
 |
フォーマルハウト(Fomalhaut)は、みなみのうお座のα星です。みなみのうお座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つです。
[由来]
秋に北半球で夜空を眺めると、天頂付近に夏の星座の名残として、夏の大三角を構成するベガ,デネブ,アルタイルの3個の1等星があるものの、南の低い空には明るい星が少なく、フォーマルハウトだけがポツンと光っているようにも見えるここから、日本では、「秋の1つ星」や「南の1つ星」などと呼ばれているそうです。 |
※ロイヤル・スター(王の星)
フォーマルハウトは、地球から23光年の距離ある星で、黄道上に位置していることから、太陽が通り過ぎたり、月が覆い隠したり、惑星が近づいたりするために、王の運命を予言する上で欠かせない星で、しし座のレグルス、さそり座のアンタレス、おうし座のアルデバランと共に、紀元前2,500年頃からペルシャでは、ロイヤル・スター(王の星)と呼ばれていたそうです。
 カペラ(Capella)の和名:すばる(昴)の相手星(壱岐)、能登星(静岡・若狭・京都)、佐渡星(富山)
カペラ(Capella)の和名:すばる(昴)の相手星(壱岐)、能登星(静岡・若狭・京都)、佐渡星(富山)
 |
カペラ(Capella)は、ぎょしゃ座のα星です。ぎょしゃ座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つで、冬のダイヤモンドを形成する恒星(6個)の内の1つでもあります。
[由来]
北東の空にカペラとすばる(昴)が同時に昇ることから「すまるの相手星」と呼び、壱岐島ではイカ漁に出てすばるが見えない時に、カペラで方角を知ったそうです。
その他にも、「能登星」や「佐渡星」の名前があるそうです。 |
 シリウス(Sirius)の和名:大星(広島・香川・高知・三重)、青星(北海道・石川)、絵の具星(岐阜)
シリウス(Sirius)の和名:大星(広島・香川・高知・三重)、青星(北海道・石川)、絵の具星(岐阜)
 |
シリウス(Sirius)は、おおいぬ座のα星であり、おおいぬ座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つです。太陽を除けば地球上から見える最も明るい恒星で、オリオン座のベテルギウス、こいぬ座のプロキオンと共に、冬の大三角を形成しています。
[由来]
日本では、見た目の様子から「大星(おおぼし)」や「青星」と呼び、その他にも、シリウスが忙しなくまたたいて色を変えることから「絵の具星」とも呼ばれているそうです。 |
 プロキオン(Procyon)の和名:色白(島根)、小さな大星(三重)
プロキオン(Procyon)の和名:色白(島根)、小さな大星(三重)
 |
プロキオン(Procyon)は、こいぬ座のα星で、こいぬ座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つで、おおいぬ座のシリウス、オリオン座のベテルギウスと共に、冬の大三角を形成しています。シリウスと比較するとやや低温(6,650K)で、プロキオンの直径は太陽の2.048倍(シリウスは1.68倍)だそうです。
[由来]
「小さな大星」は、シリウスを「大星」と呼ぶのに対して付けられ、また、島根県地方では「色白(いろしろ)」と呼び、これに対してシリウスは「南の色白」と呼ばれているそうです。 |
 ベテルギウス(Betelgeuse)の和名:平家星(岐阜)、金脇(岐阜)
ベテルギウス(Betelgeuse)の和名:平家星(岐阜)、金脇(岐阜)
 |
ベテルギウス(Betelgeuse)は赤色超巨星で、オリオン座のα星です。オリオン座の恒星で全天に21個ある1等星の1つです。おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンともに、冬の大三角を形成しています。
[由来]
岐阜の方言でベテルギウスの赤色を平家の赤旗、リゲルの白色を源氏の白旗になぞらえたと解釈され、野尻抱影は農民の星の色を見分けた目の良さに感心して、それ以後は平家星・源氏星という名前を使用するようになったそうです。
また、滋賀の虎姫(現・長浜市)でベテルギウスを金脇(きんわき)、リゲルを銀脇(ぎんわき)とする方言が発見され、これは、オリオン座の三つ星の脇にある関係とベテルギウスの金色とリゲルの白色とを見分けた表現から来ているそうです。 |
 リゲル(Rigel)の和名:源氏星(岐阜)、銀脇(岐阜)
リゲル(Rigel)の和名:源氏星(岐阜)、銀脇(岐阜)
 |
リゲル(Rigel)は、オリオン座のβ星であり、オリオン座の恒星で全天に21個ある1等星の1つで、冬のダイヤモンドを形成する恒星(6個)の内の1つです。
リゲルはβ星ですが、平均視等級の数字ではα星のベテルギウスよりも明るいそうです。
[由来]
ベテルギウス(Betelgeuse)を参照して下さい。 |
 ポルックス(Pollux)・カストル(Castor)の和名:2つ星(静岡・三重)、蟹の目(愛媛・静岡)、猫の目、金星・銀星
ポルックス(Pollux)・カストル(Castor)の和名:2つ星(静岡・三重)、蟹の目(愛媛・静岡)、猫の目、金星・銀星
 |
ポルックス(Pollux)は、ふたご座のβ星で、ふたご座で最も明るい恒星で全天に21個ある1等星の1つです。バイエル符号は、ティコ・ブラーエの星表に基づいて実視等級が明るいものからα,β,・・・と命名されていますが、ふたご座の場合にはカストルとポルックスの両方が1等級とされて、カストルがα星、ポルックスがβ星とされています。
[由来]
「2つ星」は、2つ並んだポルックスとカストルから付けられた和名で、他にも、動物などの目に見立てた「蟹の目」や「猫の目」などの呼び名があるそうです。 |
 ポラリス(Polaris)の和名:北の1つ星(青森・群馬・千葉・静岡・三重・和歌山・鹿児島)、子の星(沖縄)など
ポラリス(Polaris)の和名:北の1つ星(青森・群馬・千葉・静岡・三重・和歌山・鹿児島)、子の星(沖縄)など
 |
ポラリス(Polaris)は、こぐま座のα星であり、こぐま座で最も明るい恒星で2.005等星です。方角を知るための星であることは誰もが知っていると思います。
[由来]
「北の1つ星」は、周りに明るい星がなく、1つだけポツンと輝いていることからそう呼ばれているそうです。また、沖縄地方で呼ばわれている「子の星」は、十二支で「子」は真北の方角に相当することから付けられた名前だそうです。
この他にも、日本各地でさまざまな名前で呼ばれているそうです。 |
次は、星座や星団に纏わる名前(和名)を調べて紹介したいと思います。
 出典・参考サイト
出典・参考サイト
ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/
宙(そら)の名前 執筆者:林 完次 発行:角川書店
星をさがす本 執筆者:林 完次 発行:角川書店
日本の星「星の方言集」 野尻抱影著 発行:中央公論社
他
 星の名前(和名)と由来
星の名前(和名)と由来